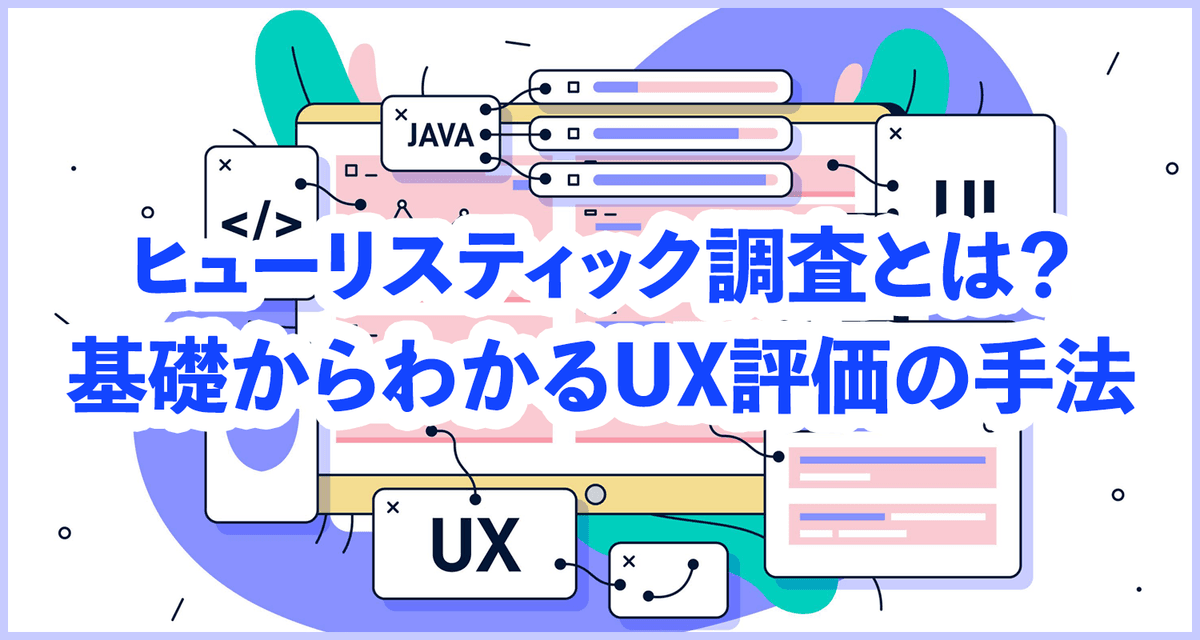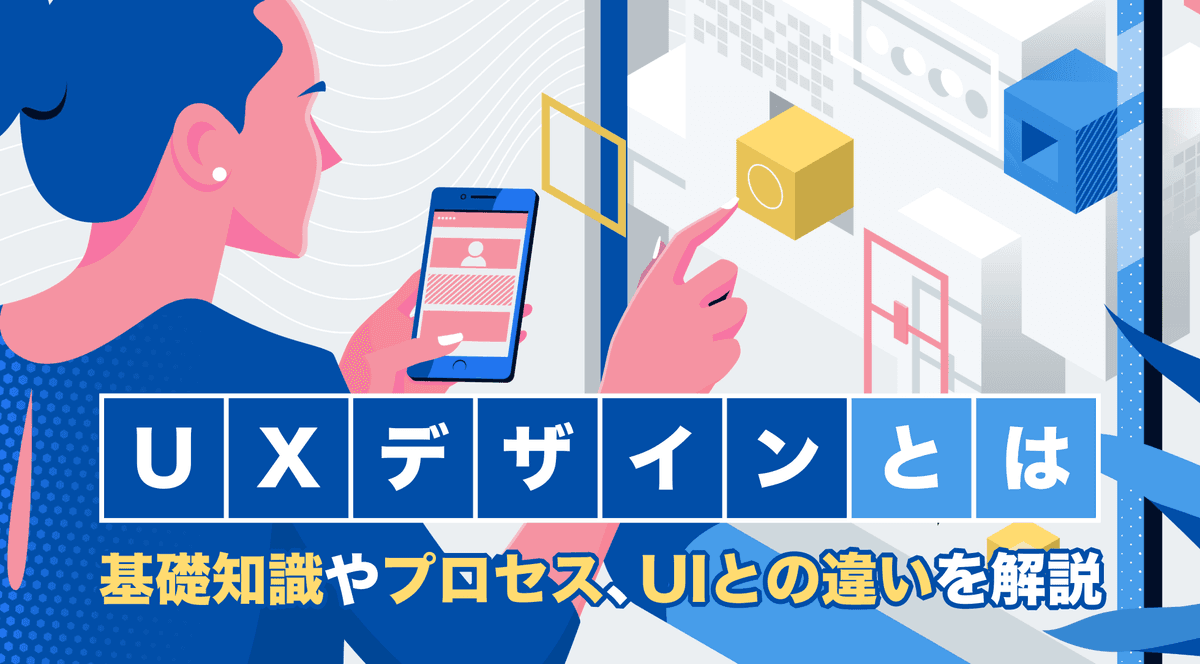ヒューリスティック調査とは?基礎からわかるUX評価の手法
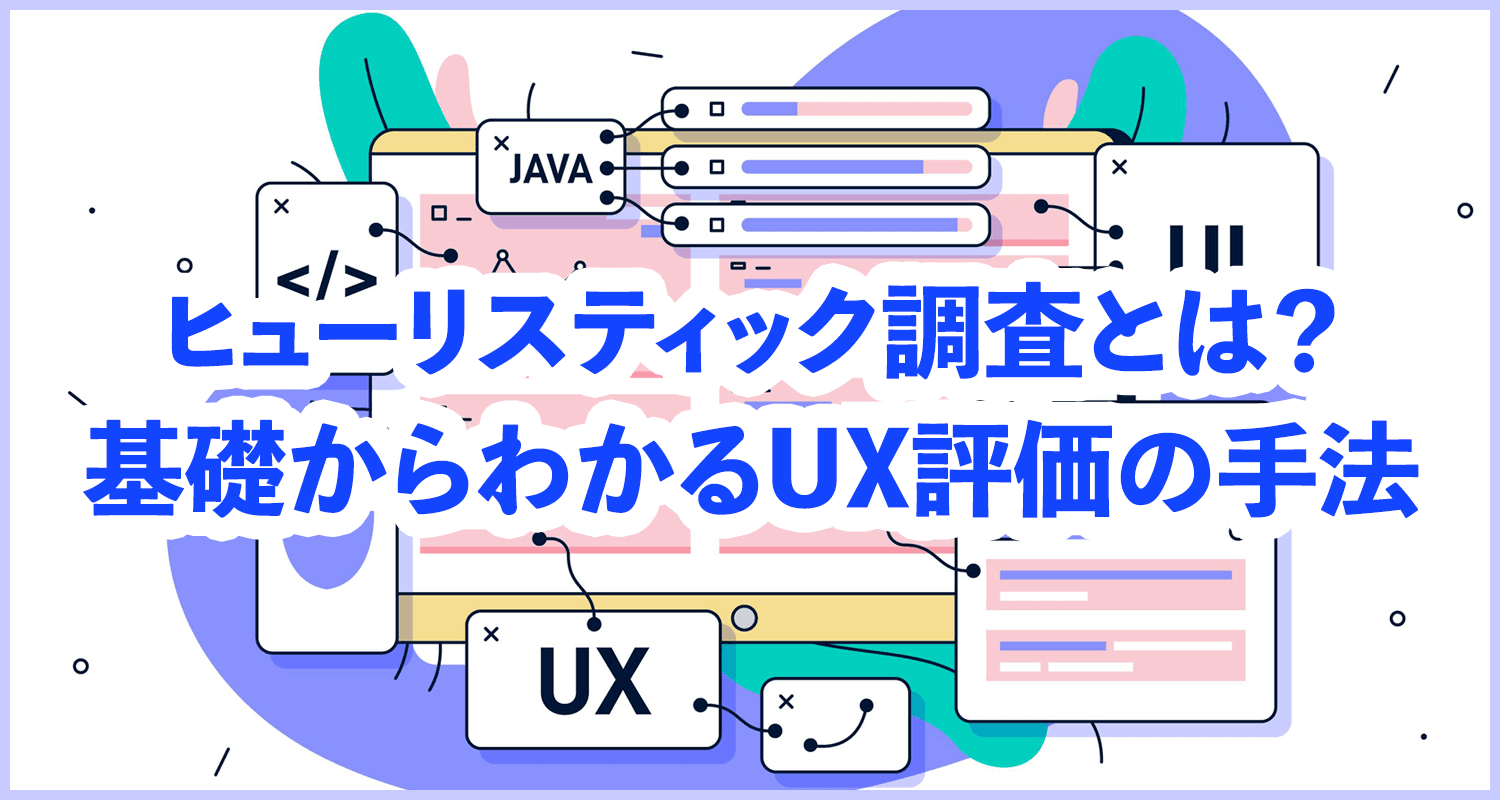
- ヒューリスティック調査とは?UX改善に役立つ評価手法をわかりやすく解説
- なぜ今、ヒューリスティック調査(分析)が求められているのか
- 活用されるシーンと期待される効果
- ニールセンの10原則に基づく評価基準とチェックポイント
- ヒューリスティック調査の進め方と具体的な手順
- 他手法との違い:ユーザビリティテストやアクセス解析との比較
- ユーザビリティテストとヒューリスティック調査の違い
- アクセス解析との違い
- ヒューリスティック調査のメリットと注意点
- ヒューリスティック調査の利点
- ヒューリスティック調査を外部に依頼する場合のポイント
- SINAPの提供するUX調査支援
- まとめ:ヒューリスティック調査を起点に“気づき”をUX改善につなげる
ヒューリスティック調査とは?UX改善に役立つ評価手法をわかりやすく解説
Webサイトやアプリの使いやすさを高めるためには、ユーザー視点での評価が欠かせません。
その中でも、WEB制作経験の豊富な制作者や、UXの専門家が経験則にもとづいてUIをレビューし、改善ポイントを洗い出す「ヒューリスティック調査」は、低コスト・短期間で実施できる有効な手法として注目されています。
こうした専門家によるUI評価は「エキスパートレビュー」とも呼ばれます。
SINAPにはHCD-Netの資格を持つスタッフも多数在籍しており、こうした専門知識を活かした評価を行うサービスを提供しています。
ヒューリスティック調査(分析)診断・改善サービス
この記事では、ヒューリスティック調査の基本から、評価基準、他手法との違い、実施プロセス、外部委託時のポイントまで、UX改善に役立つ情報を丁寧に解説します。
「ヒューリスティック評価」と「ヒューリスティック調査」の呼び方について
世の中では「ヒューリスティック評価」という呼び方も一般的に使われています。
情報設計や学術的な文脈では「評価(evaluation)」のほうが一般的ですが、明確な区別があるわけではありません。
本記事では、SINAPのサービス名称にあわせて「ヒューリスティック調査」と表記していますが、「ヒューリスティック評価」と読み替えても問題ありません。
なぜ今、ヒューリスティック調査(分析)が求められているのか
ユーザー中心の設計(UXデザイン)の重要性が増す中で、限られたコストと時間の中でも改善につながるフィードバックが得られる手法として注目されています。
特に次のような場面で、有効性が高いとされています:
- サイトやサービスの立ち上げ前にUIを確認したいとき
- リニューアル時に現状の課題を整理したいとき
- 数値では見えないUX上の問題を発見したいとき
ユーザビリティテストのようにユーザーを実際に招く必要がないため、スピーディーかつ効率的に実施できる点が強みです。
活用されるシーンと期待される効果
ヒューリスティック調査は、表面的なデザインの良し悪しだけではなく、ユーザーの離脱やストレスにつながる根本的な使いにくさを見つけるのに役立ちます。
たとえば、
- フォームが途中で放棄されている原因が、ラベルやガイドの不足だった
- モバイル表示での操作が、PC設計の流用によって使いづらくなっていた
といった問題点が発見されることは珍しくありません。ユーザー体験の質を高める第一歩として、ヒューリスティック調査は非常に有効です。
ニールセンの10原則に基づく評価基準とチェックポイント
ヒューリスティック調査を行う際、多くの現場で参照されているのが、ユーザビリティの専門家Jakob Nielsen(ヤコブ・ニールセン)が提唱した「10のヒューリスティック原則」です。
これは、UI/UXの設計や検証において指針となる経験則であり、ユーザー視点から“どこに使いにくさがあるのか”を見極めるための基準として非常に有効です。
以下に、各原則の要点とチェックポイントの一例をご紹介します。
状態の可視化 | 現実世界との親和性 |
行動の自由と取り消しのしやすさ | 一貫性のある設計 |
ミスを未然に防ぐ仕組み | 覚える必要のないUI |
柔軟で効率的な操作性 | 情報の整理と視覚的なバランス |
エラーの発見と復旧のしやすさ | 必要なときに助けが得られる仕組み |
チェックリストとしての価値
この10原則は、UX設計の基本的な考え方が集約されたフレームワークであり、調査やレビューの際に一貫した評価基準を持つことができるという点で非常に役立ちます。
特にチームでの評価や第三者レビューの場では、判断基準のブレを抑え、再現性のある分析を可能にする点が重要です。
SINAPでは、これらの原則をベースにしつつ、プロジェクトの目的やサイトの特性に応じて独自の観点を追加した調査設計を行っています。
ヒューリスティック調査の進め方と具体的な手順
ヒューリスティック調査は、比較的シンプルな枠組みで行える評価手法ですが、正確な判断と再現性のある成果を得るには、段階的なプロセスと丁寧な設計が不可欠です。
ここでは、一般的に推奨される6つのステップに沿って進め方を解説します。

ステップ1:調査の目的と対象範囲の定義
まずは、調査のゴールと評価対象をはっきりさせます。
「UIの問題点を把握したい」「改善ポイントを整理したい」など、目的が明確であればあるほど、調査内容に一貫性が出ます。対象画面や機能の範囲も事前に絞っておくと、無駄なくスムーズに進められます。
ステップ2:評価基準(ヒューリスティック)のカスタマイズ
基本はニールセンの10原則を参考にしますが、自社のプロダクトや業界特性にあわせて観点をカスタマイズすると、より有用なフィードバックが得られます。社内に過去の調査データや独自指標があれば、それも活用材料になります。
ステップ3:評価メンバーの選定と役割分担
評価の客観性を保つために、UXの専門家だけでなく、PM・エンジニア・マーケターなど多様な視点を持つメンバーを組み合わせるのが理想です。誰がどの画面を担当するかなども事前に分担しておくと効率的です。
ステップ4:実査の実施と観察
評価基準に沿って画面をチェックしていきます。
単なるチェックリストではなく、「なぜ問題と感じたか」「ユーザーはどこで迷うか」といった具体的な指摘と根拠をセットで記録します。
ステップ5:調査結果のレポート化と可視化
発見した課題を整理し、「問題点」「影響」「改善案」をまとめてレポート化します。
スクリーンショットや図解も使って、関係者に伝わりやすい内容に仕上げるのがポイントです。
ステップ6:改善施策の立案と実行フェーズへの接続
調査で得た気づきをもとに、どの改善策を優先するかを検討し、プロジェクト内で具体的なアクションへとつなげていきます。ヒューリスティック調査は“評価して終わり”ではなく、“改善のスタート地点”として活用することが重要です。
他手法との違い:ユーザビリティテストやアクセス解析との比較
ヒューリスティック調査はUXの改善に活用される代表的な手法のひとつですが、
現場では他にも「ユーザビリティテスト」や「アクセス解析」など、さまざまな評価アプローチが存在します。
それぞれに特徴と得意分野があるため、目的や状況に応じた使い分け・組み合わせが鍵になります。
ユーザビリティテストとヒューリスティック調査の違い
ユーザビリティテストは、実際のユーザーがプロダクトを操作する様子を観察し、その中から課題や改善のヒントを探る手法です。
「なぜこの操作でつまずいたのか」「どこで混乱が生じたのか」といった、ユーザー本人の行動や声に基づく“リアルな体験”が取得できます。
対してヒューリスティック調査は、UXの専門家が経験と評価基準(ヒューリスティック)に基づいてUIをレビューする方法です。
ユーザーを巻き込む必要がないため、スピードとコスト面での優位性があり、リリース前後のチェックなどにも向いています。
評価項目 | ヒューリスティック調査 | ユーザビリティテスト |
|---|---|---|
評価者 | UXの専門家 | 実ユーザー |
実施コスト | 比較的低い | 中〜高 |
実施期間 | 短期間で対応可能 | 企画〜実査で時間がかかる |
得られる知見 | 問題の仮説・設計上の懸念点 | 行動・反応・体験に基づく実態 |
アクセス解析との違い
アクセス解析では、ユーザーがどのページを訪れ、どこで離脱したかといった定量的な“行動結果”を把握できます。
しかし、数値だけでは「なぜ離脱したのか」「どこに迷いがあったのか」といった行動の背景までは見えてきません。
ヒューリスティック調査は、その“背景”を構造的に評価する手段として効果を発揮します。
たとえば、直帰率の高いページに対して、「文言が専門的すぎる」「ナビゲーションが分かりづらい」などの仮説を立てる際に役立ちます。
評価項目 | ヒューリスティック調査 | アクセス解析 |
|---|---|---|
評価者 | UXの専門家 | サイトの訪問データ(実績) |
実施コスト | 比較的低い | 低コスト |
期間 | 短期間で実施可能 | 継続的に計測 |
得られる知見 | 設計上の仮説・課題の抽出 | ページ訪問や離脱などの行動データ |
組み合わせることでより深い分析結果が得られる
これらの評価手法は、相互補完的な関係にあると考えるのが自然です。
一つのアプローチで全体像をカバーするのではなく、複数の視点を組み合わせることで、UXに対する理解が深まります。
たとえば:
- アクセス解析で離脱率の高いページを特定
- ヒューリスティック調査でUIの問題点を洗い出し仮説化
- ユーザビリティテストで仮説を実ユーザーの行動で検証
というように、段階的かつ戦略的に評価手法を組み合わせることで、改善の精度と説得力を高めることが可能です。
ヒューリスティック調査のメリットと注意点
ヒューリスティック調査は、限られた時間や予算の中でもUXの改善に役立つ手法として、多くの現場で導入されています。
ただし、活用する際には特性をよく理解し、目的に応じた設計と使い方が求められます。
ここでは、代表的な利点とあわせて、実施時に意識したいリスクや注意点を整理します。
ヒューリスティック調査の利点
- スピーディーな実施が可能
ユーザーリクルートやテスト環境の準備が不要なため、比較的短期間で評価を行えるのが大きな特長です。 - コストパフォーマンスが高い
大規模な予算をかけずに、専門的な観点でのフィードバックを得られる点で、初期フェーズのプロジェクトにも適しています。 - 設計段階でも活用しやすい
リリース後だけでなく、ワイヤーフレームやプロトタイプといった開発初期でも活用可能です。 - バイアスの排除に効果的
社内メンバーだけでは見落としがちな課題も、第三者による客観的なレビューで補完できます。
実施時の留意点
- ユーザーの実行動を直接確認するわけではない
調査はあくまで専門家の知見に基づく評価であり、ユーザー本人の感じ方や文脈は必ずしも反映されているとは限りません。 - 評価者の力量に左右される部分がある
評価の精度は、UXに対する知識や経験、ユーザー視点の理解度によって大きく差が出る可能性があります。 - 調査の対象範囲を丁寧に設計する必要がある
評価対象が広すぎたり、曖昧だったりすると、調査の質が低下し、結果的に改善への結びつきが弱くなることがあります。 - 成果を活かすための運用が重要
調査結果をまとめて終わりではなく、関係者と共有し、改善アクションとして実装までつなげることが成果に直結します。
「仮説の補助線」としてのヒューリスティック調査
ヒューリスティック調査は、“答え”を出すものではなく、課題の存在に気づくための仮説づくりを支援するツールです。
ユーザー行動の裏付けまでは得られませんが、他の調査手法と組み合わせることで、全体のUX評価の厚みが増します。
たとえば、以下のような流れが効果的です:
ヒューリスティック調査で課題を発見 → ユーザビリティテストで実際の行動を検証 → 改善案を実装・反映
“気づき”から“改善”へとつなぐための第一歩として、非常に有効なアプローチといえるでしょう。
ヒューリスティック調査を外部に依頼する場合のポイント
自社内でUX評価を実施する体制が整っていない場合、ヒューリスティック調査を専門パートナーに委託することは有効な選択肢です。
ただし、外注する際には、調査の目的に合ったパートナーを見極めると同時に、進め方や期待値を明確にしておくことが成功のカギとなります。
委託前に整理しておきたいこと
外部に依頼する際、以下のような点を事前に明確にしておくとスムーズです。
- 調査のゴール(課題発見/改善提案/検証など)
- 評価の対象となる画面や機能の範囲
- 指摘のみか、改善案まで含めるか
- レポートの活用目的(社内共有、改善の説得材料など)
こうした条件が曖昧なまま依頼してしまうと、「思っていた内容と違う」「深度が不足している」などのミスマッチが発生しやすくなります。
パートナー選定時にチェックしたいポイント
外部のUXパートナーを選ぶ際には、以下のような視点で比較・検討するとよいでしょう。
- 類似ジャンル・規模のサービスでの評価実績があるか
- 調査経験だけでなく、UX改善全体に関する知見や提案力を持っているか
- デザイン・開発チームとの橋渡しができるか(改善まで見据えた連携)
できれば、過去のレポート事例や調査プロセスを提示してもらい、アウトプットの粒度や提案の具体性を確認することをおすすめします。
おおよその費用感と期間の目安
ヒューリスティック調査のコストはどのくらいか、いくつかの企業のサービスを調べてみました。
評価対象のページ数や必要なレポート深度によって異なりますが、概ね10万〜50万円程度が一般的な価格水準のようです。
「改善施策の提案を含めるか」「短納期かどうか」などの条件によって変動します。
スケジュールの目安としては、ヒアリング〜レポート納品まで2〜3週間程度を見込んでおくのが無難です。
タイトなスケジュールでも対応可能な会社もあるため、相談時に確認しておきましょう。
SINAPの提供するUX調査支援
SINAPでは、評価観点のカスタマイズから分析、改善提案の整理、さらにUI改善案の作成まで含めたワンストップの調査支援を行っています。
単なる問題指摘にとどまらず、UXの質を実際に高めていくための実行力ある提案とサポートを重視しています。
まとめ:ヒューリスティック調査を起点に“気づき”をUX改善につなげる
ヒューリスティック調査は、UXの課題に気づくための“発見の起点”となる手法です。
実際のユーザー行動を測定する手法ではありませんが、限られた時間やリソースの中でも、UIに潜む問題を効率よく可視化できるという点で非常に有効です。
この記事では、ヒューリスティック調査の概要から評価基準の整理、他手法との違い、進め方、外部委託時の注意点までを幅広くご紹介しました。
UX改善を継続して行っていくうえで、まずは専門家によるレビューから「どこに改善余地があるのか」に気づき、次のアクションへつなげていくことが成果への近道となります。
Webサイトやアプリの使いやすさに関する評価や課題の発見など、UI・UXの専門家が調査します。
課題を明らかにした後は改善のご提案や制作まで幅広く対応いたします。
お客様のご状況に合わせた最適な解決方法をご提案いたします。まずはお気軽に、ご相談ください。